春望録
2025年 3月23日 いま日本に最も必要な物
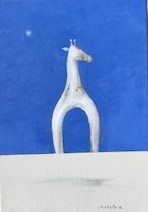
と言えば私は今日本に必要なものは法改正だと思っている。といのも3月11日に追悼式が行われた東日本大震災からすでに14年の歳月が経っている。TVでもこの時の特集が組まれ、現在の被災地の様子が映し出された。とはいえそこからすぐに感じたのは、なかなか復興が進んでいないという思いだ。因みに私は番組の中で映し出される代り映えのしない風景に過去の映像か現在の映像か区別がつかづ何度もテレビに目を近づけたほどだ。そういえば昨年の11月だったと思うが、能登地震の被災者に対する仮設住宅建設のため学校の校庭をその用地とするためようやく測量を始めたという報道があった。被災してから11か月も経って寒さがいよいよ厳しくなるというのにようやくこの状態なのだ。なぜ政府は被災者に対しこれほど冷たいのかと憤りを抑えることが出来ない。
このことに関連して別の番組では、このまま政府の支援を当てにしていられないと自ら借金をして旅館を立て直した女将の話も報道されていた。それでは、日本でさらにこのような災害が起こってしまったら一体どのような事に成るのか想像してみると、現状ではやはり復旧の目途が立たない被災地がこのまま増えていくばかりだと思ってしまう。因みに復興の進まない主な原因として考えられるのは、土地や財産の所有権の問題がある。というのも現行の法律では所有権の特定できない土地や財産は、所有者の承諾なしには、再びこのような震災が起こったとしても簡単に倒壊家屋の撤去や排除が出来ない。こうなればそのような家屋の財産はいつまでも復興の流れから外れてしまうことになる。
何を言いたいかといえば土地建物などの所有権には、このような事態を想定し速やかな復興が望める法律を整備する必要があるのではないかと言う事だ。このようなことを言えばすぐに緊急事態条項に結び付けられるかもしれないが、要するにあの法律が危険だというのは、そもそも政府は信用できないということが前提になる。だとすれば自衛隊のシビリアンコントロールも危険極まりないはずなのだが、このような心配をする方はこの点どのようにお考えなのか伺ってみたくなる。要するに事の緊急性から信用できる政府を得ることと、この話を同じに考えるべきではないと思うのだ。
と言う事をふまえ、改めて被災地において所有権が特定できない不動産がある場合、そこは地域の復興が優先されるべきと考える。つまり復興計画によっては、これに見合うだけの資産を保証することで所有者の承諾がなくても復興を優先させるという法律にしてはどうだろうか。これには金銭的な解決や代替え地などの解決など様々な解決方法が考えられ所有者はいずれかの方法を選択可能とする。
要するに震災発生時の固定資産に対する所有権は、その土地の復興が優先されるという考え方だ。このような法律的根拠があれば地方の判断により復興はより迅速に行われるに違いない。合わせて有事における不動産の所有権もこれに準じる扱いになる。とはいえこのようなことは立法府が率先して行うべき問題のはずだ。ところが、現在の国会議員にとっては夫婦別姓を必要とすることやLGBTQに対する認識の方がよほど重要らしい。そればかりかこれほど国民が心を痛めている追悼式においても眠気すら我慢できない議員がいたらしい。日本国民はこのままの状態を見過ごしていいのだろうか。