春望録
2025年 4月16日 新しい労使関係
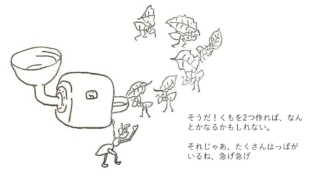
労使関係と言えば、労働者という立場と使用者という労働に対し賃金を支払う立場がある。この様な立場が鮮明になったのは、やはりブルジョワジーの登場と、その後を追うように生まれた産業革命の過酷な労働環境がこのような対立の切っ掛けになっている。そしてこの流れの対立色を更に強めることになったのが共産主義思想による共産主義国家の誕生だろう。このような流れから言えば労働組合は過酷な環境に曝され不当な富の分配に対して唯一対抗できる手段だと言える。
ところがこれについても、現在では様々な限界が見えている。というのも企業経営が安定し労働が絶対的な価値を持っている場合であれば、労働争議は絶対的威力を発揮する。ところが会社自体の経営が不安定な場合や産業自体の先行きが見えない場合はどうだろうか、労働争議はむしろ雇用の喪失というジレンマに陥ってしまわないだろうか。
このような環境になれば、当然使用者側の立場も理解しなければ雇用そのものが危うくなるのである。以前であれば、このような立場を取る組合は御用組合という汚名を着せられてきた。さて今日労働組合活動はこのような流れで確実にその勢力を弱めてきている。そのため組合主導の労働争議など見聞きすることも稀になった。それにあわせるように労働者の組合加入率も年々減少しているのだという。確かにどれほど過酷な労働条件になっても組合がこれを唯々諾々と鵜呑みにしているようでは、組合運動は選挙活動と思われても仕方がない。
そこで私は世界に先駆け日本はこれまでの労使関係を改めてはどうかと考えている。どういう事かと言えば現在労働者は憲法によりその権利を保障されている。一方企業が憲法で保障されているのは、結社の自由の自由ぐらいしか思い浮かばない。
もしそうだとすれば労働者の立場は国が直接守らなければおかしなことになる。そこでこれまでのように労使関係は二つの対立構造ではなく、国を間に挟み憲法に則り労働者の労働環境を守ってはどうかと考えている。
もしこうなれば、これまでのように社員が出社して入り口の張り紙で初めて自社の倒産を知ると言う悲劇は防げるのではと思う。
具体的にいえば労働者側の代表は国の専従とする機関と自社の労働環境改善の交渉に入る。そしてこれを受け国が企業と待遇改善について交渉を持つのだ。この場合企業が環境改善不可能の理由を示せば、この差を当面国が必要度に応じて対処する。例えばその企業が経営の問題を訴えれば、これについて国がその解決策を労使に対して示すことになる。例えば企業が資金繰りに困っていればその溝を国が社債購入で埋めるか、或いは最悪経営改善の目途が立たないと判断されれば、憲法に則り労働者の最低限の生活を守りつつ速やかに会社の整理に当たることが出来る。
このような仕組みが役に立つのは、現在のように一斉に賃金上昇を起こさなければならなくなった場合、企業により足並みが揃わないことで、かえって賃金格差により社会に歪が起こってしまう。このような取り組みが行われていれば、このようなリスクを抑えることが出来るはずだ。また、労働環境が企業の規模によりまちまちであることは日本国憲法の理念に反すると言えるだろう。このように世界的にも労使が対立する構図は、国が積極的に国民の雇用を考え生活の向上に関わることで、国と国民との絆が深まる。そして、これまでの労使の対決姿勢は、労使が協調して国や企業の未来を見つめるという新たな社会トレンドを促すことが出来るだろう。
現在与野党で政党内の分裂が起きているが、その原因を辿れば政府や政党と言う立場にしがみ付こうとする人たちと、国民の代表と言う立場で政策に国民の思いや願いを届けようとする政治家の違いに見えてくる。これまで有権者は政党と言うオブラートで政治家の行動を許してきた。現在起こっている分裂騒ぎはこれに対する政治家の正直な答えだろう。