今昔問答
2025年 4月6日 今昔問答
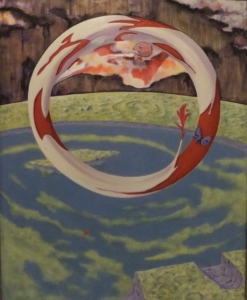
落語にコンニャク問答と言うのがある。無理やり住職にさせられた豆腐屋と修行の旅に出た禅僧が丸三角四角のジェスチャーで極めて難解な禅問答を成立させてしまうというお話しで、今の世の中は同じ言葉でも受け取り方でまるで違った意味を共有してしまう風刺に思える。さてそんな落語の隠された意味を受け取りながら、たっぷり楽しめるのが落語研究会の放送だ。
今回の放送では春風亭一之輔氏の花見酒、人間国宝五街道雲助氏の駒長、古今亭文菊氏の鹿政談、立川龍志氏の寝床と言う演目で、最初の花見酒は花見酒の経済という笠信太郎氏の書籍があるほど笑い話の中にも社会風刺が潜んでいるようだ。とはいえそんな堅苦しいことは抜きにして、一之輔氏の美味しそうに酒を飲む仕草は落語という虚構ならではの楽しみだ。因みに今回の放送で全体を通して特に印象に残っているのは江戸庶民の暮らし向きである。よく聞く宵越しの金は持たねぇという江戸っ子の啖呵も江戸時代は福祉が進んでいた証拠というより、信用における経済が発達していたと言う事ではないかと思う。つまりこの時代の庶民は銭を出して生活を営むというより、ツケと言うローン社会が成熟していたというこだろう。この花見酒でも無一文の人間が借金に追われている身にも拘らず、さらに借りを作って商売をしようと言う呆れた話だが、そんなことが出来たのも主人公の返済計画を酒屋が納得し信用したからに他ならない。つまり江戸時代はすでに信用貸しによる経済が理解され成り立っていたということになる。
また鹿政談は司法の公平性について現代の我々に伝えているようだ、つまりこの話は司法は国民あっての司法と言う事を言いたいのではないだろうか。最後の寝床も良かれと思ってのことも己を知らなければ社会には多大な損害を与えてしまうという戒めに感じる。
このような江戸庶民の生活にさらにシビアな切り口でドラマ化しているのが今放送されている大河ドラマの「べらぼう」ではないだろうか。私もこれまで大河ドラマは見てきたつもりだったが、これほど挑戦的な切り口のドラマを知らない。何せそもそも吉原と言う特殊な遊郭の出来事から始まり、これに眉を顰める視聴者も少なからず居られるはずなのだ。前回の放送でも私はこれまで聞いたこともない座頭貸しと言う高利貸しの話が登場してきた。つまりこれまでの歴史認識では田沼意次時代と言えば金権まみれの悪政というステレオ認識しかなかったがそれでは正しい歴史認識にはならないと言う事が理解できる。つまり、このドラマを視ればそのような一方的な歴史認識では、歪な歴史認識に至ってしまう可能性があるのだ。このことから時代の息吹を少しでも正確に伝えようというスタッフの意気込みが伝わってくる。私は日本がそのような志を持った人達の活躍できる社会であって欲しいと願っている。