今昔問答
2025年 5月13日 セットでなけりゃ意味ないよ!
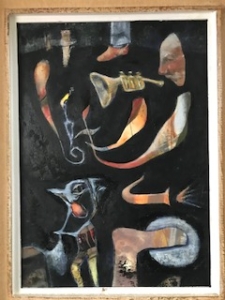
最近、巷では消費税に対する風当たりが強くなっているが、私も日本経済の再生の鍵はここに有ると思っている。とはいえ国会では減税や廃止を訴える議員は増えてきているものの、法人税を上げろという声はほとんど耳にしない。因みに私は、この取り組みは法人税増税とセットでなければ、この取り組みはむしろ逆の効果になる危険性さえあると思っているのだ。
つまり減税と言えば必ず問題にされる財源をキッチリ示さなければ、後々そのしっぺ返しが国民に重く圧し掛かってくる。これについては国債で解決できるという見方もあるが、国債発行は一般会計の支出である公債費も同時に膨らませてしまうので、結局予算の中身を萎ませてしまう欠点がある。私は国の予算は出来るだけ前向きな支出で検討されるべきと思うので、国債発行についてはある程度の歯止めは必要と考えている。
とはいえ選挙前に増税しろということをこの時期声高に主張するのは、かなりの抵抗を受けるはずだ。このことで驚く発言をされたのが今、話題沸騰の西田議員なのだが、経済発展のカギを握る議員の国会発言が、あろうことかひめゆりの塔に掛かる歴史認識問題ですっかりかき消されてしまっている。かたや直ちに国民生活を左右するはずの国会発言より、憲法のシンポジウムで発言された、歴史に対する個人認識がマスコミに取り上げられ大いに話題になっている状態だ。私がこれらの現象に違和感を感じるのは、この攻撃に参加している側の面子を見れば、何故か人間の性別に関しては、個人の認識を重視するべきだという方々が多いという認識を持っている。
このまま、このような不条理が国の政策に影響を持つようになれば、我々国民の生活は一体どのようになってしまうのか、考えなくともヨーロッパの主要国を見れば想像がつくところだ。ところで、西田議員が国会で発言されたのは消費税の廃止とその財源を法人税の増税で補うというものだ。これを聞くと個人の負担を、法人に肩代わりさせるイメージに受け取られるかもしれないがそうでは無い。この前提になるのは消費税は誰が払っているのかという問題だ。これについて政府の認識は、消費税は第二法人税だという認識なので、消費税も企業が直接納めている税という認識になっている。つまり、現在企業は消費税と法人税を別々に計算して納税している状況にある。これを法人税という一つの計算方法に集約し納税していただくことが、法人にとっても個人にとっても、しいては日本経済にとっても想像できないほどのメリットを生むことに繋がると思っている。何のことはないこれは日本の景気が良かったころの税制に戻せと言う事にすぎないのだ。
では過去の税制に戻すことで考えられるメリットを挙げてみると、まず第一に考えられるのは、物価を押し下げる効果で、これについての異論はないだろう。もう一つがこれにより、直ちに賃金上昇が見込まれることだ。ようするに消費税は必要経費が認められない欠陥税制なのである。つまりこれを廃止することによって企業は人件費を増やし節税効果を狙うはずで、これにより役員報酬も含めた即効性が期待できる。結局その分、税収が減るのではと思われるかもしれないが、その分は個人所得としてガラス張りのサラリーマンが支えているので、これ以上取りっぱくれの心配はない、それよりも個人所得が増えることは保険料収入に直結しているため年金問題なども同時に改善されるはずだ。さらに個人収入が増え景気循環が活発になれば、小売り業での価格転嫁が容易になる。というのもいま最も窮地に立たされているのは、薄利多売で利益をようやく確保してきた食堂が、食材の高騰を価格に転嫁出来ず苦しんでいる。この状況を改善してもらうためにはサラリーマンの小遣いを倍にしていただく政策が是非とも必要になるのだ。もしこのまま、まともな政策が行われなければ、商品の値上げは外食産業全体の客離れを起こしかねない。
これは大袈裟な表現ではなく、実際にコンビニ全体の衰退という社会現象がこれを示している。以前の記事にコンビニの入店客数が変わらなくてもお客がお金を使ってくれないということを扱った。本来このような事態を経団連は認識していなければならないはずなのが、むしろ経団連は日本の経済を衰退させてきた消費税増税を推進している状況なのだ。このような外国かぶれの団体が政府に物申す制度自体、日本企業全体がもう一度考えるべき時に来ていると思う。
つまり日本の経済復興には政府による未来産業への投資の他に、日本企業による社員へのインセンティブをどのように高めていくかという問題もこれから海外との競争に勝ち抜くための重要な問題になるだろう。そのためには法人税の簡素化が日本経済の復興に役立つと思うのだ。