日々これ切実
2025年 9月13日 芸の極み
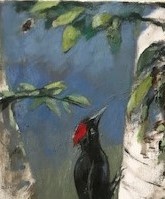
時々こちらの想像を超えた芸を見せつける人がいる。ジャグラーの大道芸なども、こちらの想像を超える驚くような芸を見せつけられてしまうと、たとえ通りすがりのつもりであっても、その場を動くことが出来なくなる。
とはいえ、そこまで突飛な世界でなくても、伝統芸能と言われる落語でも弛まぬ挑戦によってその型を越えようとする噺家に出会う。
先日も落語研究会の番組で、話芸でありながら話さない芸があることに気付かされた。一般的には間の芸といわれているのかもしれないが、高座に上がり座布団に座った瀧川鯉昇氏が一瞬言葉に詰まった様子をみて、研究会の会場から自然と笑いが起こっていた。これだけの事なのだが、落語研究会というところは、落語のプロからしてもなかなか特殊な環境のようでここではお客さんが笑わないと溢す噺家さんをよく目にしてきた。そんな鯉昇氏の演目は「馬のす」という、これまた解説の宮信明氏が言うには、落ちを聞いたらそれまでという単純な話だという。逆に言えば、この話を最後まで引っ張るにはやはり噺家の技量が試されることになるはずだ。恐らくそれが試されるのは、馬の尻尾を抜くとどんなお咎めがあるのか、この含みの持たせ方が、観客の興味を最後まで引っ張れるかどうかの差になってくる。私も氏の話術にすっかり乗せられ、その落ちを聞きたくて仕方がなかった。さて続いて登場の三遊亭夢丸氏は「冥途の喧嘩」を演じる。夢丸氏といえば落語研究会でも馴染の顔だが、さすがにおどろおどろしい幽霊の話を落語という洒落の世界にすっきりと納めてくれた。さて真打昇進の松柳亭鶴枝氏、演目は有名な「ろくろくび」だが、この話も荒唐無稽な話で、客の興味を最後の落ちまで引っぱるには、どれだけ客の想像力を掻き立てることが出来るかに掛かってくる。この話では特にろくろ首であるお嬢さんの美しくしさと、その恐ろしさを描き切る技量が求められている。
ところでトリの春風亭一之輔氏の演目は「かんしゃく」という演目で、氏が枕で断りを入れていた通り、観客によっては物議を醸してしまいそうな噺だ。内容は小言念仏に近いが、話に自家用車が登場してくるので時代はより近年に近づいてくる。とはいえ、あえてこの演目を落語研究会で披露するところが、一之輔流の落語に対する挑戦状だろう。結局これだけ罵声の連発する落語なのにも拘らず、淡々と演じきれるのも並々ならぬ技量というしかない。伝統芸能といえばまるで型通りの世界のように感じてしまうが、その世界の中でも輝く人はやはり、現状への挑戦を怠らない人達のようだ。