日々これ切実
2025年 11月3日 茶席と吉田松陰
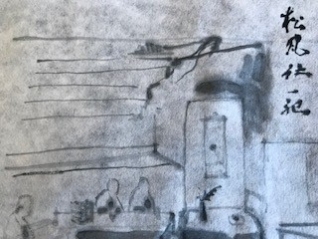
昨日は文化の日に相応しく函館市民文化祭にお邪魔しお茶を頂いた。この日お茶席を設えてくれたのは裏千家談交会の方々だ。恥ずかしながら私は還暦を過ぎた身でありながら、これまでお茶の素養などまるで関わることがなかった。そのためようやく事前にYouTubeをみてお茶の頂き方を学んだくらいで、ほぼ、外国の観光客と変わるところがない。それにしても茶事いうものを普段の生活から眺めると、まるで秘められた儀式のようでもある。一体お茶を飲むだけの行為になぜあれだけの時間と労力を掛けなければならないのか、デジタル化が進む現代の生活においては、その異様さは特に際立つように思える。
それにしても茶席といえば和装の方々の装いに、むき出しのコンクリートの壁も何故か和んで見えるのには驚いてしまう。ここに漆を用いた漆黒のお盆や、何気に下げられた暖簾が普段の練習室を見事に作り変えてしまっていた。それにしても床の間などの無い室内に軸などどのように飾られるのか想像もできなかったが、移動式のパネルを巧みに使い立礼式の茶席が見事に整えられていた。さて、今年の函館は一気に冷え込みが来たために紅葉の時期にも関わらず色の冴えない景色となっている。運ばれてきた生菓子もこの景色合わせてか淡い色あいで装われていたが、餡の鹿子が牛皮で包まれているなど枯葉にうずまる外の景色宜しく複雑な食感を楽しむことが出来た。
話は変わるが、日本文化といえば、武士道という言葉を思い浮かべる方も少なくないだろう。というのも海外の方が日本文化を理解しようとすれば、いまでも新渡戸稲造氏の著書「武士道」に学ばれる方も少なくないと思うからだ。ところで、これも偶然なことだが、茶会に伺う前に私はYouTube動画で配信されている「偉人の流儀というチャンネル」の【士規七則】武士たる者の心得という配信を観ていた。私はこの動画により吉田松陰が命を懸けて伝えたかったことは、人として生きるためにもっとも大切にしなければならないことは、人を思いやる心だと学んだ。つまりここに心を込めて生きることが至誠に繋がるということなのだ。
今回偶然にもこの思いの冷めやらぬうちに、茶事における作法を学ぶことで、すべての作法が客と亭主それを支える人への感謝であることを知った。つまりあの不思議な作法とは、客が心の限りを尽くして感謝を亭主に伝えることであり、亭主もその思いを丁寧に受け取ろうとすることにあるようなのだ。このやり取りが、月日を重ねさらに洗練され、現代にまで伝わっているように感じた。
このような普段の喧騒とはまるでそぐわない世界における茶道だが、その歴史を辿れば、それは平和な時代において生まれたというより、戦国における明日の命も危ぶまれる時代に誕生した文化であることも興味深い。因みに裏千家といえば先日、大宗匠千玄室氏が亡くなられたばかりだ。氏は特攻に向かう仲間の求めに応じ、その場で茶を立てたという。特攻といえば自分の命を捨てる覚悟ばかりか、人の命を奪うことも受け入れなければならないという過酷さがある。そんな極限の世界においても最後まで人間としてありたいという願いが、茶事に対する最後の願いであり千玄室氏はその思いを受け止め精一杯の思いでお茶を立てていたのではないだろうか。