独立自尊 奥の細道

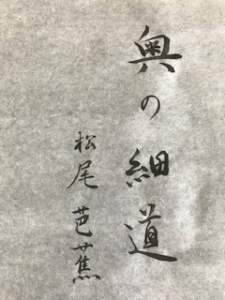

奥の細道 序文について

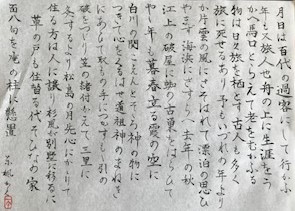
この投稿は自分の勝手な思いを綴った極めて私的な文章ですので、学問の世界とは無縁の文章です。特に学生の方はご注意下さい正解は教科書にあります。とはいえそれが正解だとしても物足りないという方には、驚く解釈が次々登場しますので楽しんでいただけるのではと思います。できればこれを機会に奥の細道という日本文学の至宝を味わう切っ掛けになればという思いです。
さてこれを書こうと思った切っ掛けは、俳句を絵画として表現することにそもそもの目的がありました。ところがいざ始めてみるとその俳句が何を表現しているのかさえ理解できません。結局奥の細道にある文章や曽良の日記などを参考に、時代背景や当時の風習なども考慮しなければここに登場する句は味わい尽せないことに気付きました。そんな思いで多方面から奥の細道の世界を考察していくと、これまで自分が勝手に作り上げていた奥の細道とは全く異質な世界に迷い込んでしまったように感じます。最後はとんでもない結果になりますのでどうぞお楽しみください。ただしR15かも知れません。
さて奥の細道といえば、俳句よりも有名な序文があります。この文章は私も小学校の頃暗記を試みた記憶があります。結局頭に残っていたのは最初と股引を繕ったところです。ところで、その時から私はこの文章に違和感を感じる箇所が何点かありました。なかでも特に違和感を感じる所は舟の上に生涯を浮かべという文章と馬口とらえてという文章です。確かにこれらは昔の旅には付きものだったかもしれませんが、最後の集大成となる奥の細道にわざわざ採用する必要を考えれば、よほど重要な意味が含まれているように感じます。
そこでこの文章を芭蕉のあこがれる西行の生い立ちに重ねてみると、このような比喩も理解できそうに思います。というのも西行法師は徳大寺家との繋がりがあり日蓮宗からの影響も強く感じられます、このことから大乗仏教の表現である一乗の舟をイメージさせる舟の上に生涯を浮かべという表現は理解できます。また、衆生を仏門に導く僧としての姿を馬子という表現で表しているようにも思えます。
そして、このような西行の生い立ちは後に武家との関りにも感じます。というのも後に奥の細道から藤原氏、佐藤氏、源氏などとの繋がりを感じるからです。
それでは早速ですが、初めの句は次回探ることにして、巻末に登場する「表八句を庵の柱に掛け置く」とはどのような意味なのか考えてみます。
私はこの文の意味を芭蕉がすでに詠んだ八つの句を杉風の庵の柱に掛け置いたと解釈していました。ところが、不思議なことに残りの7つにあたる句がどこにも見つかりません。では誰かが失くしてしまったのか、それもないでしょう芭蕉は当時からすでに神の如くあった人でその遺品をめぐっては大騒ぎになるほどの方です。
ではどうしてしまったのか、私の答えは初めからそれにあたる句は無かったという解釈です。というのもこの当時世の中に俳句というものは存在していません。あったのは俳諧という言葉遊びに近い集まりです。俳諧とは歌を繋いで楽しむ遊びで、連歌の会と言った方が分かり易いと思います。
この会で詠まれた歌は、懐紙という紙に書いて残されますが、この懐紙とは大ぶりの半紙のようなものです。俳諧ではこれに宗匠から順番に歌を記していきます。つまり表八句とは八つの俳句が書かれていたのではなく、俳諧の初めとなる宗匠の句を懐紙にしたため、柱に掛けて置いたということではないでしょうか。さてこうなると次に誰が歌を記すことになるのかが問題になります。というのも場合によってはこの順番で蕉風一門の序列が決まってしまうからです。
さらに言えば奥の細道にはわざわざ杉風の別墅とありますので、杉風の別墅に掛けてあったたのであれば当然杉風の句が残されていいはずです。もしそんなものが残っていれば、これは芭蕉のお墨付きになるはずで、これほど有難いものは有りません。俳句を志す者には下方以上の価値になるでしょう。因みにこのころ杉山杉風は、すでに同門の嵐雪と揉めていたそうです、ということはこのことを芭蕉は知り杉風の方を持ちたかったが、そうはいかなかったという見方は出来ないでしょうか。